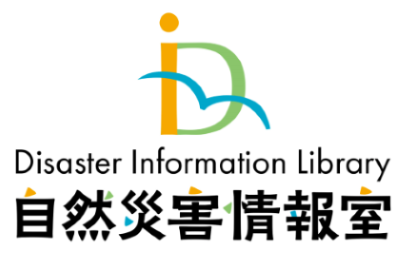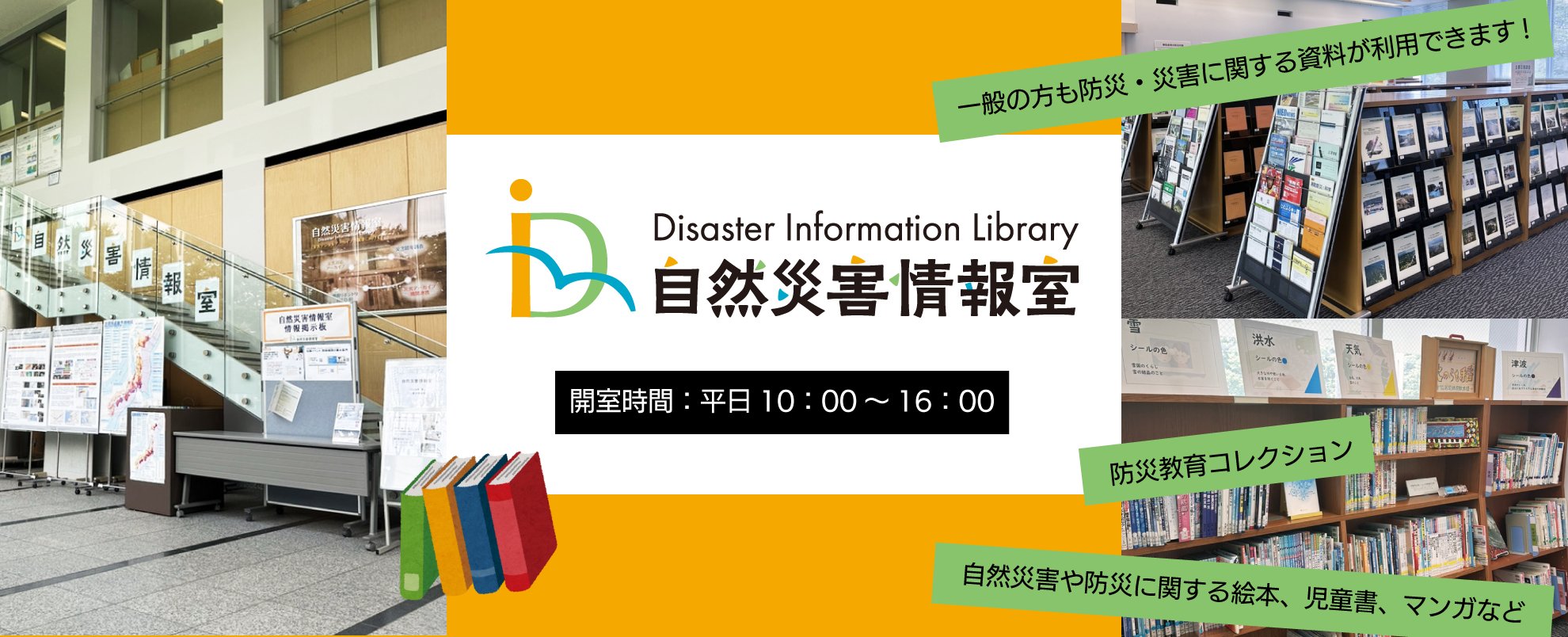- 2025年10月22日(水) 10:00-18:00 ブース在席
- 2025年10月23日(木) 10:30-12:00 フォーラム開催(アネックスホール第4会場) 12:00-18:00 ブース在席
- 2025年10月24日(金) 10:00-18:00 ブース在席
防災科学技術研究所(防災科研)とは?
1963年に設立された自然災害・防災に関する国立の研究機関です。あらゆる種類の自然災害(オールハザード)を対象に、災害発生前後の全ての段階(オールフェイズ)について総合的な研究開発を進めています。
自然災害情報室ってどんなところ?
自然災害情報室では防災・災害に関する資料の収集・提供を行う専門図書館としての機能のほか、災害直後とその経年変化を記録する現地調査、発災時の災害対応情報収集・整理、機関リポジトリの運用、災害アーカイブ機関との連携、防災科研の主要研究誌編集など幅広い業務を行っています。
平日10:00-16:00は、どなたでも閲覧室(つくば市)の利用ができます。<開館カレンダー>
<10月22-24日会場開催は終了いたしました>
防災科研ブースへ お立ち寄りいただき誠にありがとうございました。。
展示物についてのご質問・貸出のご相談等は下記フォームよりお問い合わせください。
◆10月23日に開催された防災科研フォーラムページ
フォーラムの一部講演資料はオンライン第2期終了(10月23日)までの公開です。
◆全国の災害アーカイブ実施図書館
出展内容
展示ホールC 防災科研 自然災害情報室ブース【小間№66】
「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨から学ぶ」
自然災害情報室では、現在「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨から学ぶ」をテーマにした企画展示を開催しています。図書館総合展ブースではこの展示の一部をご覧いただけます。
学校・地域の防災教育に「防災教育コレクション」はいかがでしょうか?
<防災基礎力を高め、実践力を養い、未来につなぐ防災の寺子屋>として、自然災害のメカニズムや防災教育に関する資料のコレクションを約4,000点所蔵しています。「防災教育コレクション」は皆様の防災教育活動にお役立ていただくため、団体向けの貸出を実施しています。
今回ブースには、住まいのそなえ「片付け×防災」を扱ったコレクションをご用意してお待ちしています。
《関連フォーラムのご案内》
令和6年能登半島地震の調査写真アーカイブや防災教育コレクションの活用事例について
2025年10月23日(木)開催のフォーラム
「「忘れない」を仕事にする— 図書館・学校・地域で活かす《災害アーカイブ》」
の講演でもふれます。奮ってご参加ください!
★災害資料アーカイブ機関の連携に参加しませんか?
防災科研では、災害資料を収集・整理・保存・提供する機関間の連携をサポートし、アーカイブ運営に関する知見を共有・蓄積するために、メーリングリストを運営しています。ご興味がある機関の方はブースにてお声がけください。また下記お問い合わせフォームからもご相談可能です。
現在参加されている45機関の一覧は自然災害情報室webページでご覧いただけます。
「防災パネル・防災教育コレクション」または「自然災害情報室の利用」「災害資料アーカイブ機関の連携」に関するご質問は、上記フォームよりお気軽にお問い合わせください。
展示ホールC 「災害と図書館2025」
災害・防災に関する複数団体の企画が会場内の1つのコーナーにまとめて展示されています。
-
「全国の災害アーカイブ実施図書館」
主催:図書館総合展運営委員会 共催:防災科研
日本全国の災害アーカイブを持つ機関をご紹介。
お住いの近くにどんな災害アーカイブがあるのか、どんな災害が過去にあったのかを知る機会に。
-
防災科研以外の団体の企画
みんなで育てる図書館災害救急BOX 主催:図書館総合展防災関係出展チーム
その他の参加企画
-
「あなたも使える専門図書館2025」
主催:図書館総合展運営委員会、協力:(株)ブレインテック
会場とオンライン両方で自然災害情報室の紹介パネルが公開されます。
<過去の図書館総合展出展内容>
◆2024年(パシフィコ横浜会場)
自然災害情報室 ブース紹介
【スピーカーズコーナー】研究者制作・監修!防災パネルミニ展示
◆2023年(オンライン)
研究者制作・監修!防災パネル展示
防災教育コレクション
関東大震災に関する所蔵資料
◆2022年(オンライン)
【災害と図書館2022】災害発生!あなたならどうする?~水害編~
◆2021年(オンライン)
東日本大震災10年 災害アーカイブのこれまでとこれから
・「災害アーカイブを語る」
・「HOW TO 災害アーカイブ」
・災害アーカイブ担当者インタビュー:「東日本大震災災害アーカイブの10年」
◆2020年(オンライン)
「災害発生!あなたならどうする?」
◆2019年(パシフィコ横浜会場)
「災害アーカイブの発展と継承 ~東日本大震災を例に」
防災ワークショップ:「災害発生!あなたならどうする?」
◆2018年(パシフィコ横浜会場)
西日本豪雨災害 緊急報告会~被災地図書館からの報告